☆山岡鐡舟(1836~1888)
山岡鐡太郎。本所に生まれる。父小野朝右衛門高、母塚原磯(先祖に塚原ト伝)。幼少から神蔭流、北辰一刀流、浅利義明の門下となり、維新後は無刀流の開祖となる。
幕臣として清河八郎と共に浪士隊を結成。江戸無血開城に深く関与。明治政府では静岡藩権大参事、茨城県参事、伊万里県権令、侍従、宮内大丞、宮内少輔を歴任。
1882年(明治15年)、16代徳川家達は無血開城の功として鐡舟に名刀「武蔵正宗」を贈与した。
Ⅰ-3.勝・山岡・西郷の鼎談

【海舟・南洲 会見之地】
3月13日、幕府の陸軍総裁勝海舟は供一人だけを伴って、大総督府参謀の西郷隆盛が待つ高輪の薩摩藩邸へ向かった。
勝は口舌の徒ではない。だから、「大西郷」と言われる男に対して、青二才の
ごとき説得をしようとは端から思っていなかった。気概と作戦。これで臨んだのであったが、作戦が効いたと思われるのは、山岡を使者として派遣したこととパークスへの手紙であったものと推定された。しかし、これからもっと効いてくるのは江戸焦土作戦のはずである。官軍が攻め入ろうとすれば、自ら火を点けるという江戸っ子の抵抗は、官軍のやろうとしていることが民衆の支持なき革命ということになる。ということは今は官軍の名を冠してはいるが、対抗勢力が台頭したとき、逆転する可能性がないでもない。ということに、あの「大西郷」なら気付くはずである。攻めている方が、攻められている方に試されていることが・・・・・・。
海舟が部屋に案内され、暫くしてから西郷が山岡鐡太郎を伴って入ってきた。
「勝先生。遅うなって、すんません。」
山岡は西郷が江戸に入ってから、護衛として付きっきりだった。もし徳川方が西郷を襲撃したり、暗殺したりするような事態になれば、これまでのことが水の泡となる。
部屋では三人が鼎座の形となった。
この日、勝は、もし戦争が起きた場合は、故14代将軍家茂の正妻・静寛院宮(皇女和宮親子内親王)の処遇をどうするかだけを話題にした。他のことについては一切触れない。これも勝一流の謎掛であった。知られる通り、和宮は皇女が武家に降嫁し、関東に下向した唯一の方である。だから、敬意をもって処すというのであった。加えて、慶喜は水戸へ蟄居させると先の『七ケ条』で申し入れている。この二つをもって、われわれが〝皇国日本〟の立場を選んだことぐらい分かるだろう。勝は常に、物事の大・中・小、一番・二番・三番を見分ける判断力に長けていた。だから、この大事なことに比べれば、他のことは紙切れに書かれた雑多のこと、そんなものは話し合えば何とでもなるではないか。それよりも、今のわれわれは日本人として諸外国から〝皇国日本〟を守らなければならないときだろう、と静寛院宮の処遇を通じて勝は言っているのである。
西郷は勝の思いを察知した。「今日のところは、これくらいにしときまッしょう。勝先生、山岡先生。寿司ドン喰うていかんですカ。江戸前バ、取ットリマスケン。」〝江戸前〟・・・・・・、少なくとも西郷の段階では「江戸は守る」との意志の表現であった。
山岡が両目を閉じて天井を仰いだ。
4月11日、かくて江戸城は新政府に引き渡され、最後の徳川将軍(15代)慶喜は水戸へ落ちて行った。1603年に家康が開府して以来265年続いた徳川時代、イヤ鎌倉以来780年続いた封建時代がついに終止符を打ったのであるから、これ以上の歴史的平和的鼎談はないだろう。
しかしながら、維新は成っても、火は燻っていた。会津藩や、上野寛永寺の義観率いる彰義隊という、最も〝徳川〟的な人たちの反抗であった。
鐡太郎も、「一死、君家の難に殉ぜん」と、新政府軍に立ち向かう気持もわからなくはなかった。しかし、「幕臣」という立場を越えて「日本丸」という船に乗り、本物の〝憂国の情熱〟をもってほしいと諭すが、かなわなかった。
彼らは血祭りにあげられ、散っていった。
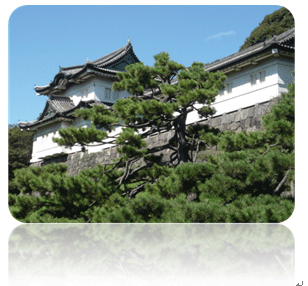
【現在の皇居】
|
前のページ Ⅰ-2.山岡・西郷の会談 |
コンテンツのトップ |
次のページ Ⅱ. 三舟の書の事 Ⅱ-1.大坂屋砂場 |









