
°°ЄёЈо
љ’≤觻љ’Ћ№
°°єЊЄЌ§ќ¬зµ»Єґ≈Є§ѕјєґЈ§ќ§и§¶§«§в§Ґ§л°£§»§ѓ§ЋЉг§§љчј≠§ѕґљћ£ƒ≈°є§ј§» є§ѓ°£їд§ §…§ѕµ»Єґ≈Є§» є§ѓ§»ЉЂЌ≥§ їю¬е§Ћ§ §√§∆Јлєљ§ §≥§»§ј§»ї„§¶°£
°°°÷љ’≤и°„§ѕ√Ћљч§ќЊрЄт§т…Ѕ§§§њєЊЄЌїю¬е§ќ∆щ…Ѓ≤и§д»«≤觫§Ґ§к°Ґ°÷љ’Ћ№°„§ѕ§љ§м§й§ђЋ№§ќЈЅ§Ћ§ §√§њ§в§ќ§«§Ґ§л°£°÷љ’Ћ№°„§Ћ§ѕ°Ґ°÷•п∞х° §Є§л§Ј°Ћ°„°÷±рЋ№° §®§у§Ё§у°Ґ§®§џ§у§»§в°Ћ°„°÷≤«∆юЋ№° §и§б§§§к§№§у°Ћ°„§ §…§ќ ћЊќ§ђ§Ґ§л°£§Ђ§ §к∞ Ѕ∞°Ґ∆ьЋ№ґбј§ Є≥Ў≤с§ќЄ¶µж»ѓ…љ§«Љг§§љчј≠Є¶µжЉ‘§ђ°ҐЅЌ° §Ќ§Ї§я°Ћ§ќ≤«∆ю§т…Ѕ§§§њ≥®Ћ№§Ћ§ƒ§§§∆°÷≤«∆юЋ№°„§»ѕҐЄ∆§Ј§∆µп ¬§÷«ѓ«џЉ‘§њ§Ѕ§ђґмЊ–§µ§ї§й§м§њ§≥§»§ §…§тї„§§љ–§є§ђ°Ґ≤«∆юЋ№§»§ѕ°Ґ¬зћЊ§ §…§Ў≤«∆ю§є§лЇЁ§Ћ≤÷≤«§Ћ•„•м•Љ•у•»§є§лј≠ґµ∞йљс§ђљ’≤и°¶љ’Ћ№§«§в§Ґ§√§њ§≥§»§Ђ§й°Ґ§≥§ќЄ∆Њќ§ђ§Ґ§л°£
°°§≥§ќ§и§¶§ євµй¬£≈ъ… §«§в§Ґ§√§њљ’≤и§дљ’Ћ№§ѕ°Ґ…вј§≥®ї’§њ§Ѕ§ќјЇє™§ ∞хЇюµїљ—§ќњи° §є§§°Ћ§тњ‘§ѓ§Ј§њм‘¬ф° §Љ§§§њ§ѓ°Ћ§ §в§ќ§«§Ґ§√§њ°£
°°єЊЄЌїю¬е°Ґљ’≤и°¶љ’Ћ№§ѕ°Ґ±£§µ§м§∆§§§њ§в§ќ§«§в§ §ѓ°ҐґЎїя§µ§м§∆§§§њ§в§ќ§«§в§ §Ђ§√§њ°£Ї£§ќЋ°ќІ§д≤Ѕ√Ќі—§Ђ§й§є§л§»°Ґ≤њ§Ђ°÷§§§±§ §§§в§ќ°„§«§Ґ§л§Ђ§ќ§и§¶§ ∞хЊЁ§тЉх§±§л§ђ°ҐєЊЄЌ§«§ѕ°Ґљ’≤и°¶љ’Ћ№§ђ¬з§й§Ђ§Ћ¬ЄЇя§«§≠§њ°£§љ§м§ѕ°ҐЉ“≤с§ђј≠§Ћ§ƒ§§§∆§Ђ§ §к≥Ђ ь≈™§«§Ґ§√§њ§ђЄќ° §ж§®°Ћ§ќЈл≤ћ§«§в§Ґ§л°£≥Ђ ь≈™§»Єј§¶§»ћо ь§Ј§ќ§и§¶§ ∞хЊЁ§тїэ§њ§м§л§Ђ§в√ќ§м§ §§§±§м§…°Ґј≠§вњЌі÷§ќјЄ≥и§ќ∞м…ф§«§Ґ§л§»єЌ§®§∆§§§њ§ќ§«§Ґ§л°£
°°јоћш§Ћ°÷єІє‘§Ћ«д§й§м…‘єђ§ЋјЅљ–° §¶§±§ј°Ћ§µ§м°„§»§§§¶Ќ≠ћЊ§ ґз§ђ§Ґ§л°£ґв§Ћµз§Ј§њњ∆§ђћЉ§тµ»Єґ§ЎЌЈљч§Ћ«д§к°Ґ§љ§ќЌЈљч§ђ ь∆Ґ¬©ї“° §џ§¶§»§¶§а§є§≥°Ћ§ЋјЅљ–§µ§м§л»й∆щ§ ЄљЊЁ§т±”° §и°Ћ§у§ј§в§ќ§«§Ґ§л§ђ°Ґљ’§т«д§л«дљ’§ќƒЃ°¶µ»Єґ§«°ҐєЊЄЌїю¬е§ѕљчј≠§ќј≠§ђ∆≤°є§»«д«г§µ§м°Ґ§љ§≥§Ћ»біоЈа§ђ§Ґ§√§њ°£
°°§»§≥§н§«°ҐєЊЄЌїю¬е°Ґ≤њ≈ў§Ђ§ќљ–»«Љиƒщќб§«°÷є•њІЋ№° §≥§¶§Ј§з§ѓ§№§у°Ћ°„§ќґЎїя§ђлр° §¶§њ°Ћ§п§м§∆§§§л§«§ѕ§ §§§Ђ§»§™§√§Ј§г§лЄю§≠§в§Ґ§н§¶°£љ’≤и°¶љ’Ћ№§ќ эћћ§ќ ™√ќ§к≤»§ѕ°Ґє•њІЋ№§ђ§є§ §п§Ѕљ’Ћ№§ј§»єЌ§®§∆§§§л§и§¶§ј§ђ°Ґ§Є§ƒ§ѕ°ҐЇ£≤у§ќ≈ЄЌч≤с§ќ§и§¶§ љ’Ћ№§ѕ°Ґљ–»«Љиƒщќб§ќ¬–ЊЁ§«§ѕ§ §Ђ§√§њ°£Ћл…№§ѕ°Ґј≠…ЅЉћ§ЋіЎ§є§лљ–»« ™§ќјљЇоі©є‘§Ћ§ƒ§§§∆§ѕ°ҐЋлЋц§ё§«¬з§й§Ђ§Ћћџ«І§Ј§∆§§§њ§ќ§«§Ґ§л°£љ–»«Љиƒщќб§Ћ§и§√§∆Љи§кƒщ§ё§й§м§њ°÷є•њІЋ№°„§»§ѕ°ҐњІ≥є§ §…§т…с¬ж§ЋЉ“≤с…ч¬ѓ§тЌр§є§и§¶§ ∞ь° §я§ј°Ћ§й§ ЊЃјв§ќ∞в° §§§§°Ћ§«§Ґ§√§њ°£
°°
°°§њ§ј∞м≈ў§ј§±°Ґљ’Ћ№§ђє•њІЋ№§»§Ј§∆Љи§кƒщ§ё§й§м§њ§≥§»§ђ§Ґ§√§њ°£§љ§м§ѕ°ҐЋлЋц§ќ≈Ј Ё§ќ≤ю≥„§ќїю°Ґ°÷§і¬Є§Є±уї≥§ќґв§µ§у°„§≥§»ƒЃ фє‘±уї≥ґвїЌѕЇ§Ћ§и§√§∆§«§Ґ§л°£Љг§§љчј≠§њ§Ѕ§ђћі√ж§Ћ§ §√§∆∆…§я§’§±§√§њќш∞¶ЊЃјв§«§Ґ§лњЌЊрЋ№° §Ћ§у§Є§з§¶§№§у°Ћ§»∞мљп§Ћ°Ґљ’Ћ№§в ≤љс° §’§у§Ј§з°Ћ§µ§м°Ґ»ƒћЏ§ѕЊ∆§≠Љќ§∆§й§м§∆§Ј§ё§√§њ§ќ§«§Ґ§л°£±уї≥ґвїЌѕЇ§ѕ°Ґ§≥§ќ§и§¶§ Ћ№§ђ§Ґ§л§Ђ§йј§§ќ√ж§ќ…ч¬ѓ§ђЌр§мљ–§Ј§њ§»§§§¶ЌэЌ≥§ќ§в§»°Ґљ’Ћ№§ё§« ≤љс§є§л§»§§§¶•“•√•»•й°Љ ¬§я§ќЌ¶§я¬≠§т§Ј§∆§Ј§ё§¶§п§±§«§Ґ§л°£§≥§ќ§≥§»§ѕ°Ґјџ√ш°Ўў‘¬§° §Ќ§ƒ§Њ§¶°Ћ§µ§м§њ•“°Љ•н°Љ°Ґ±уї≥ґвїЌѕЇ°ў° ЊЃ≥ЎіџњЈљс°Ћ§ЋЊ№§Ј§ѓљс§§§њ§ќ§«°Ґ§љ§Ѕ§й§т§ії≤Њ»§§§њ§ј§≠§њ§§§»ї„§¶°£
°°
°°ЋлЋцЇҐ§Ћ§ §л§»°Ґљоћ±§ќ•в•й•л§ђЌр§м§∆§§§л§»ЊІ§®§лїў«џ≥ђµй§ќ…рїќ§њ§Ѕ§≥§љ°Ґ§»§ѓ§Ћ≤Љµй…рїќ§њ§ЅЉЂњ»§ђЈ–Ї—≈™§ЋЇ§µз§Јљ–§Ј°ҐћЉ§ќњ»«д§к§вƒЅ§Ј§ѓ§ §ѓ§ §к°Ґ§љ§м§ж§®±уї≥§ќґв§µ§у§ќє•њІЋ№јђ»≤§»§ §√§њ§ќ§«§Ґ§л°£
°°§љ§Ј§∆§µ§й§Ћ°ҐћјЉ£∞ єя°Ґ•и°Љ•н•√•—§ќј≠•в•й•л§ђїэ§Ѕєю§ё§м°Ґј≠…ч¬ѓ§ђ±£»щ° §§§у§”°Ћ§«§“§њ±£§Ј§Ћ§µ§м§лїю¬е§»§ §к°ҐєЊЄЌ§ќљ’≤и°¶љ’Ћ№§ѕƒє§ѓƒјћџ§тґѓ§§§й§м§лїю¬е§ђ§ƒ§≈§§§њ§ќ§«§Ґ§л§ђ°Ґ§и§¶§д§ѓ…вј§≥®§ќЈЁљ—ј≠§ђ«І§б§й§м°Ґ§≥§у§Ћ§Ѕ§тЈё§®§њ§п§±§«§Ґ§л°£

Ґ•ї≥≈мµю≈Ѕ° §µ§у§»§¶§≠§з§¶§«§у°Ћ≤и°Ў±рЋ№ЋнЄјЌ’° §®§џ§у§ё§ѓ§й§≥§»§–°Ћ°ў° ≈Јћј£µ«ѓ°“£±£Ј£Є£µ°”і©°Ћ§и§к°£ їЈґґ§ќЊе§«µЇ§м§л√Ћљч°£ЇЄЊе§Ћ°÷§Є§д§¶§ј§у° Њй√ћ°Ћ§т§Ј§ §µ§у§–§Ј° їЈґґ°Ћ§ќ§ё§у√槫§“§и§ƒ§»§≥§н° ≈Њ°Ћ§–°µ§§§Ђ§Ћ§ї§у§…§¶° Ѕ•∆ђ°Ћ°„§»§Ґ§л°£
≈Ј Ё§ќ≤ю≥„°ƒ≈Ј Ё«ѓі÷° £±£Є£≥£∞°Ѕ£і£і°Ћ§Ћє‘§п§м§њЋл…№°¶љф»Ќ§ќјѓЉ£≤ю≥„°£≈Ј Ё£±£≤«ѓ° £±£Є£і£±°Ћ°ҐѕЈ√ж° §н§¶§Є§е§¶°Ћњећо√йЋЃ° §њ§ј§ѓ§Ћ°Ћ§Ћ§и§√§∆√еЉк§µ§м°ҐЈрћу°¶…ч¬ѓљЌјґ§ §…§ќ≈эј©§ђє‘§п§м§њ§ђ°Ґ√йЋЃ§ќЉЇµ”§Ћ§и§к√жїя§µ§м§л°£
±уї≥ґвїЌѕЇ°ƒ£±£Ј£є£≥°Ѕ£±£Є£µ£µ°£єЊЄЌЋціь§ќЋлњ√°£ЇЄ±“ћз∞”° §µ§®§в§у§ќ§Є§з§¶°Ћ°£ћЊ§ѕ±∆Єµ° §Ђ§≤§в§»°Ћ°£ґвїЌѕЇ§ѕƒћЊќ°£і™ƒк фє‘° §Ђ§у§Є§з§¶§÷§Ѓ§з§¶°Ћ°¶ЋћƒЃ фє‘§ §…§тќт«§§Ј°Ґ≈Ј Ё§ќ≤ю≥„§тЉ¬є‘§Ј§њ°£њећо§ќЉЇµ”Єе§ѕ°Ґ∆оƒЃ фє‘§»§ §л°£
њЌЊрЋ№°ƒєЊЄЌї‘ћ±јЄ≥и§ќќш∞¶§дњЌЊр§ќ≥л∆£§т…ЅЉћ§Ј§њЊЃјв°£ Єјѓ° £±£Є£±£Є°Ѕ£≥£∞°ЋЇҐ§Ћ»ѓјЄ§Ј°Ґ≈Ј Ё«ѓі÷§тЇ«јєіь§»§Ј§∆°ҐћјЉ£љйіь§ё§«¬≥§§§њ°£¬е…љЇоЉ‘§ќ∞ў± љ’ње° §њ§б§ §ђ§Ј§е§у§є§§°Ћ§ѕ°Ґ≈Ј Ё§ќ≤ю≥„§«»≥§ї§й§м§л°£
ї≤єЌљсј“°д
°¶√™ґґјµ«о° ґ¶√ш°Ћ°ЎєЊЄЌ§ќµЇЇо≥®Ћ№≠£°ў √ёЋа≥ЎЈЁ ЄЄЋ2024
°¶√™ґґјµ«о° ґ¶√ш°Ћ°ЎєЊЄЌ§ќµЇЇо≥®Ћ№≠Ґ°ў √ёЋа≥ЎЈЁ ЄЄЋ2024
°¶√™ґґјµ«о° ґ¶√ш°Ћ°ЎєЊЄЌ§ќµЇЇо≥®Ћ№≠°°ў √ёЋа≥ЎЈЁ ЄЄЋ2024
°¶√™ґґјµ«о√ш°Ўµ»Єґ§»єЊЄЌ§≥§»§–єЌ°ў §Џ§к§Ђ§уЉ“2022
°¶√™ґґјµ«о√ш°Ўї≥≈мµю≈Ѕ§ќ≤Ђ…љїж§т∆…§а°љєЊЄЌ§ќЈ–Ї—§»Љ“≤с…ч¬ѓ°ў §Џ§к§Ђ§уЉ“2012

√ў§ё§≠≈вњ…ї“
°° Їщ§ќµ®јб§ђљ™§п§л§»°Ґ•ђ°Љ•«•Ћ•у•∞§ќµ®јб§«§Ґ§л°£
ќ–§ќ•Ђ°Љ•∆•у§ђ≤∆§ќ•®•≥¬–Їц§»§Ј§∆њдЊ©§µ§м°Ґ•ў•й•у•ј§дƒн§«•і°Љ•д§д•Ў•Ѕ•ё§ §…§т∞й§∆§л э§в¬њ§§§ј§н§¶°£≤∆§Ћ§≥§м§й§ќЌ’§т»Ћ°є° §Ј§≤§Ј§≤°Ћ§»»Ћ§й§ї§л§њ§б§Ћ§ѕ°ҐЇ£ЇҐ°ҐЉп§т§ё§Ђ§Ќ§–§ §й§ §§§ђ°Ґ§ƒ§§§ƒ§§ЋЇ§м§∆§Ј§ё§¶§≥§»§ђ§Ґ§л°£«я±Ђ§ђ≤б§Ѓ§∆§Ђ§й§Ґ§п§∆§∆…ƒ§т«г§√§∆§≠§њ§ќ§«§ѕ°Ґ≤∆§ќ•®•≥°¶•Ђ°Љ•∆•у§Ћ§ §й§Ї§Ћљ™§п§√§∆§Ј§ё§¶°£
°°
їюµ°§Ћ√ў§м§∆§Ј§ё§¶§≥§»§т°Ґ°÷√ў§ё§≠≈вњ…ї“° §»§¶§ђ§й§Ј°Ћ°„§»Єј§¶°£°÷√ў§ё§≠°„§ѕ°÷√ў§ѓЉђ° §ё°Ћ§ѓ°„§≥§»°£
≈вњ…ї“§ќЇѕ«Ё§ѕЉп§т§ё§ѓїюµ°§ђћд¬к§«°ҐЊѓ§Ј√ў§м§л§»°Ґ«Ѓ¬”√ѕ э§ђЄґїЇ√ѕ§ј§±§Ћ∆ьЋ№§«§ѕ∆ьЊ»їюі÷§ђ¬≠§к§ §§§ї§§§Ђ°Ґњ…ћ£§ђ§»§№§Ј§ѓ§ §к°Ґ≈вњ…ї“§ќЉ¬§ђ§ƒ§Ђ§ §ѓ§ §л§≥§»§в§Ґ§л°£їюјб§Ћєз§√§њЉп§ё§≠§т§Ј§ §Ђ§√§њ°÷√ў§ё§≠≈вњ…ї“°„§ѕ°Ґ•‘•к•к§»§є§лњ…§я§ђЊѓ§ §§§≥§»§Ђ§й°Ґµ§§ђ»і§±§∆§§§л§≥§»§д°ҐЇ£§“§»§ƒ»њ±ю§ќ√ў§§њЌі÷°Ґі÷»і§±§ Љ‘§т§µ§єЄјЌ’§Ћ§в§ §√§њ°£
∆ж§Ђ§±§«§ѕ°Ґ°÷√ў§ё§≠≈вњ…ї“°„§»≥Ё§±§∆°÷≤÷§ѕЇй§±§…§вЉ¬§ђ§ƒ§Ђ§Ї°„§»≤т§ѓ§ќ§ѕ°Ґ√ў§ё§≠≈вњ…ї“§ѕ•‘•к•к§»§Ј§њЉ¬§ђ§ƒ§Ђ§ §§§»§§§¶§п§±§«§Ґ§л°£
°°
≈вњ…ї“§ѕ°Ґ£±£ґј§µ™»Њ§–§Ћ•Ё•л•»•ђ•лњЌ§ђ∆ьЋ№§Ћ≈Ѕ§®§њ§»§є§лјв§в§Ґ§л§ђ°Ґ¬јєёљ®µ»° Ћ≠њ√љ®µ»°Ћ§ђƒЂЅѓљ– Љ§Ј§њЇЁ°Ґ∆Љ≥иїъ§ќ∞хЇюµ°§ §…§»∞мљп§Ћ≈вњ…ї“§ќЉп§т∆ьЋ№§Ћїэ§ЅµҐ§√§њ§≥§»§Ђ§йЇѕ«Ё§ђ§ѕ§Є§ё§√§њ§»§§§¶јв§ђЌ≠ќѕ§«§в§Ґ§л§ђ°Ґ≈вњ…ї“§в∞хЇюµїљ—§в°Ґ∆ьЋ№§Ў§д§√§∆Ќи§њјлґµї’§ђЅб§ѓ§в§њ§й§Ј§њ§»§§§¶§ќ§ђЉ¬Њр§Ћґб§Ђ§н§¶°£
іЎјЊ§«§ѕ°÷євќпЄ’№•° §≥§¶§й§§§≥§Ј§з§¶°Ћ°„§»Є∆§–§м§∆§§§њ§и§¶§«§Ґ§л° євќп§ѕјќ§ќƒЂЅѓ»Њ≈з§ќєсћЊ°Ћ°£іЎ≈м∞ Ћћ§«§ѕ°÷∆о»Џ° § §у§–§у°Ћ°„§»§вЄ∆§–§м§њ°£
°°
ґб§і§н§«§ѕЈгњ…•й°Љ•б•у§ §…§дЈгњ…•є°Љ•„§ќќЅЌэ§ђќЃє‘° §ѕ§д°Ћ§√§∆§§§∆°Ґњњ§√ј÷§ •є°Љ•„§ќ•й°Љ•б•у§тіј§т§Ђ§≠§ §ђ§йњ©§ў§л•Ј°Љ•у§ђ•∆•м•”§ §…§«Њ“≤𧵧м§∆§§§л§ђ°Ґ§љ§ќЈгњ…§ќ§в§»§ѕ≈вњ…ї“§«§Ґ§л°£
°°єЊЄЌїю¬е§Ћ§ѕ°Ґ∆в∆£њЈљ…° ЄљЇя§ќњЈљ…ґињЈљ…Єж±с°Ћ§«Їѕ«Ё§µ§м§л≈вњ…ї“§ђ≤¬… ° §Ђ§“§у°Ћ§«°Ґ°÷∆в∆£≈вњ…ї“°„°÷∆о»ЏЄ’№•°„§»Є∆§–§м°ҐєЊЄЌ§√ї“§ќƒЅћ£§»§µ§м§њ§и§¶§«§Ґ§л°£
єбњ…ќЅ§»§Ј§∆§ѕњ…ћ£§ќ¬е…љ§«°Ґ§≥§м§ЋЄ’№•°¶ƒƒ»й° §Ѕ§у§‘°£•я•Ђ•у§ќ»й§ќі•§Ђ§Ј§њ§в§ќ°Ћ°¶≥©ї“° §±§Ј°Ћ°¶ЇЏЉп° § §њ§Ќ°Ћ°¶Ћг§ќЉ¬°¶ї≥№•° §µ§у§Ј§з§¶°Ћ§ §…§тЇ’§§§∆ЇЃ§Љєз§п§ї§њ°÷ЉЈњІ≈вњ…ї“°„§ѕєЊЄЌїю¬е§Ђ§й§и§ѓї»§п§м§∆§§§л°£
°÷ЉЈњІ≈вњ…ї“«д§к°„§ѕ°Ґј÷§§¬з§≠§ ≈вњ…ї“§ќЈЅ§т§Ј§њ¬ё§т§Ђ§ƒ§§§«° њё»«ї≤Њ»°Ћ°Ґ
°Ў §»§у§»§у≈вњ…ї“°Ґ§“§к§к§»њ…§§§ђї≥№•§ќ і° §≥°Ћ°Ґ
§є§ѕ§є§ѕњ…§§§ђЄ’№•§ќ і°Ґ≥©ї“§ќ і°ҐЄ’Ћг° §і§ё°Ћ§ќ і°Ґƒƒ»й§ќ і°Ґ§»§у§»§у≈вњ…ї“°ў
§»§§§¶«д§кјЉ§«≥є√ж§т«д§к ⧧§∆°ҐњЌµ§§ђєв§Ђ§√§њ°£
°°§»§≥§н§«°ҐєЊЄЌїю¬е§ќњЉјоЌЈ≥«§«§ѕ°÷≈вњ…ї“§тњ©§п§ї§л°„§»§§§¶±£Єм° √зі÷∆в§ќЄјЌ’°Ћ§ђ±©њ•ЈЁЉ‘(√§ћ¶ЈЁЉ‘°ҐњЉјоЈЁЉ‘)§ќ§Ґ§§§ј§«ќЃє‘§Ј§∆§§§њ°£
њЌ§т§ј§ё§є§≥§»§тЄј§√§њ§ќ§ј§ђ°Ґ§љ§ќ§≥§≥§н§ѕ°Ґ≈вњ…ї“§ј§±§Ћњњ§√ј÷§ •¶•љ§»§§§¶∞’ћ£§Ђ°Ґњ…° §Ђ§й°Ћ§§ћ№§Ћ§Ґ§п§ї§л§»§§§¶§≥§»§ §ќ§Ђ°Ґ§љ§ќ§Ў§у§ѕ…‘ћј§«§Ґ§л°£

Ґ•јо§Ћ§ѕ§ё§√§њњм§√ І§§§тљх§±§л≈вњ…ї“«д§к°£
°÷њ…° §Ђ§й°Ћ§≠ћњ°„§т≈вњ…ї“«д§к§ђµя§¶§»§§§¶•Є•з°Љ•ѓ°£
ї≥≈мµю≈Ѕ° §µ§у§»§¶§≠§з§¶§«§у°Ћ§ќ≤Ђ…љїж° §≠§”§з§¶§Ј°Ћ°ЎЄжл–јчƒєЉчЊЃћж° §™§у§Ґ§ƒ§й§®§Њ§б§Ѕ§з§¶§Є§е§≥§в§у°Ћ°ў
° µэѕ¬£≤«ѓ°“£±£Є£∞£≤°”і©°Ћ§и§к°£

єЊЄЌ§ќ•ў•є•»•ї•й°Љ§»…’ѕњ
°° GW° •і°Љ•л•«•у•¶•£°Љ•ѓ°Ћ§»Є∆§÷§Ћ§в°Ґ§≥§ќ•≥•н• ≤“§«§ѕЎя° §ѕ§–§Ђ°Ћ§й§м§л§ђ°ҐѕҐµў§вћј§±§л§»љс≈є§д•≥•у•”•Ћ•®•у•є•є•»•Ґ§Ћ ¬§у§«§§§лњЈЉ“≤сњЌЄю§±§ќ•’•°•√•Ј•з•уї®їп§в«д§м§л§«§Ґ§н§¶°£
•‘•√•Ђ•‘•√•Ђ§ќЊЃ≥Ў∞м«ѓјЄ§ђ°Ґљ≈§њ§љ§¶§Ћ«Ў…й§√§∆§§§њ•й•у•…•ї•л§в°Ґ§Ј§ј§§§Ћ»ƒ§Ћ§ƒ§§§∆§ѓ§лµ®јб§»§ §√§њ°£
°° Єљ¬е§«§ѕ°Ґї®їп§ѕ∆ьЋ№Ѕієсƒ≈°є±Ї°є§ё§«√ў§м§л§≥§»§ §ѓ«џЅч§µ§м°Ґљµі©їп§ §…§ѕЅієс∆±їю»ѓ«д§ђ≈ц§њ§кЅ∞§Ћ§ §√§∆§§§л°£§Ј§Ђ§Ј°Ґ•»•й•√•ѓ Ў§ §…§ §Ђ§√§њєЊЄЌїю¬е§ѕ°ҐЅієс§«Ћ№§т∆±їю»ѓ«д§є§л§»§§§¶§≥§»§ѕћµЌэ§«§Ґ§√§њ°£
°°
єЊЄЌїю¬е»Њ§–§є§Ѓ°Ґ¬зњЌ§ќ•≥•я•√•ѓ§»§Ј§∆њЌµ§ ®∆≠§Ј§њ°÷≤Ђ…љїж° §≠§”§з§¶§Ј°Ћ°„§ѕ°ҐјµЈо§ќі©є‘Ќљƒк§«§Ґ§√§њ§ђ°ҐєЊЄЌ§«§ѕЅб§§§»§≠§Ћ§ѕ£±£±Јо§Ђ§йі©є‘§µ§м§∆§§§∆°Ґ»«Єµ§ѕ л§м§Ћ§Ђ§±§∆Ѕієс§ќЋ№≤∞§ЎЅч§л≈ƒЉЋЄю§±§ќЋ№§ќ»ѓЅч§Ћ¬зЋї§Ј§«§Ґ§√§њ°£
°° єЊЄЌ§«§ѕ°ҐјµЈоЄю§±§ќЋ№§ѕ£±£≤Јо≤Љљ№§Ћ§ѕ∆…Љ‘§ќЉк§Ћ∆ѕ§≠°ҐєЊЄЌ§Ђ§й±у§§√ѕ э§«§ќ«д§кљ–§Ј§ѕјµЈо∞ єя§ј§√§њ°£Ї£§ќЈоі©їп§ђ°Ґ£іЈоєж§»§Ј§∆§§§л§ќ§Ћ§“§»ЈоЅ∞§ќ£≥Јо§Ћ«д§й§м§∆§§§л§ќ§ѕ§љ§в§љ§в°ҐєЊЄЌїю¬е§ќі©є‘ ™§ђ√ѕ э§Ћ§и§√§∆•њ•§•а•й•∞§ђ§Ґ§√§њ°Ґ§љ§ќћЊїƒ§«§в§Ґ§л°£
°° §љ§¶§Ј§њїцЊр§Ђ§й°Ґ√ѕ э§«§“§»ЈоЄе§ЋЄЂ§й§м§лі©є‘ ™§т°÷Јо§™§ѓ§м°„§»Њќ§Ј§∆§§§њ°£єЊЄЌ§ќ¬яЋ№≤∞§«§ѕ°Ґі©є‘Єеі÷§в§ §ѓ∆ѕ§§§њњЈЋ№§ќЄЂќЅ° §±§у§к§з§¶°£•м•у•њ•лќЅ°Ћ§ѕєв§Ђ§√§њ°£§љ§м§ђ°Ґ§“§»Јо√ў§м§«ЉЏ§к§л§»°Ґ°÷Јо§™§ѓ§м°„§»§§§¶§≥§»§«ЄЂќЅ§ѕ∞¬§ѓ§ §√§њ°£
°°§љ§у§ §≥§»§Ђ§й¬ѓЄм° •є•й•у•∞°Ћ§«°Ґѕ√¬к§Ћ§є§∞§Ћ»њ±ю§«§≠§ §§§и§¶§ њЌ§т§Ђ§й§Ђ§√§∆°÷Јо§™§ѓ§м°„§»Єј§√§њ°£»њ±ю§ђ∆я§§њЌ§т°÷Ј÷Єч≈ф°„§»Єј§√§њ§ќ§Ћїч§∆§§§л§ђ°ҐЇ«ґб§ѕЈ÷Єч≈ф§в•∞•н°Љ•й•у•„§ђ§Ґ§к£ћ£≈£ƒ§Ћ§ §к°Ґ°÷Јо§™§ѓ§м°„§»∆±ЌЌ°Ґ∆я§§њЌ§т§§§¶°÷Ј÷Єч≈ф°„§вїаЄм§Ћ§ §к§Ђ§±§∆§§§л°£
°°
°°єЊЄЌїю¬е§ѕ±њЅчЉк√ §ђЄ¬§й§м§∆§§§њ§Ђ§й°Ґљ–»«»«Єµ§ђ¬њ§Ђ§√§њєЊЄЌ§дµю≈‘°¶¬зЇд§»°Ґ¬Њ§ќ√ѕ э§»§«§ѕЋ№§ќ«дљ–§Ј§ќ•њ•§•а•й•∞§ѕЋд§б§и§¶§ђ§ §Ђ§√§њ°£§љ§м§«§вЋлЋц§Ћ§ §л§»°Ґ°÷≈ƒЉЋЅч§к°„§»§§§¶Ћ№ЌҐЅч§ќјмћзґ»Љ‘§вЄљ§м§њ§й§Ј§ѓ°Ґ»«Єµ§ѕ¬яЋ№≤∞Єю§±§ќЋ№§ќЌҐЅч§тЌ•ји§µ§ї§њ°£¬яЋ№≤∞Єю§±§ќЋ№§ѕ°ҐЌҐЅч§д∆…љс§ќЇЁ§ќљэ§я§Ћ¬—§®§й§м§л§и§¶§Ћ∆√ЅхЋ№§»§ §√§∆§™§к°Ґ≤њ«№§Ђ§ќєв√Ќ§««д§м§л§Ђ§й§«§Ґ§√§њ°£
∆ьЋ№§«Ї«¬з§ќћЊЄ≈≤∞§ќ¬яЋ№≤∞¬зЅЏ° §ј§§§љ§¶°£¬зћо≤∞ЅЏ»ђ°Ћ§ѕ°Ґ£≤Ћь…ф§тƒґ§®§л¬яЋ№§тЌ ° §и§¶°Ћ§Ј§∆§§§њ¬яЋ№≤∞§«°ҐƒЏ∆внцЌЏ° §ƒ§№§¶§Ѕ§Ј§з§¶§и§¶°Ћ§в¬зЅЏ§ќ≤ЄЈ√§ЋЌб§Ј§њ§»Єм§√§∆§§§л°£ЄљЇяїƒ§µ§м§∆§§§л¬зЅЏµм¬Ґ§ќ≤Ђ…љїж§ §…§ѕ°ҐЄљЇя°Ґєсќ©єс≤сњёљсіџ§Ћ¬њ§ѓљк¬Ґ§µ§м§∆§§§∆°Ґ§љ§м§й§ѕєв§§•м•у•њ•лќЅ§ЋЄЂєз§√§њќ©«…§ Ѕх÷мЋ№§«§Ґ§л°£
°°¬яЋ№≤∞§Ћ§ѕ≥дєв§««џЋ№§«§≠§њ§»§Ј§∆§в°ҐєЊЄЌїю¬е§ќЅієс§ќ¬яЋ№≤∞§ќњф§ѕ§≠§ё§√§∆§§§∆°ҐЉыЌ„§ЋЄ¬§к§ђ§Ґ§√§њ°£•ў•є•»•ї•й°Љ§Ћ§ §л§Ћ§ѕ°Ґ∞м»ћ§ќ∆…Љ‘§ќіЎњі° іњњі°Ћ§т«г§√§∆»ѓє‘…фњф§тњ≠§–§µ§ §±§м§–§ §й§ §§°£єЊЄЌ§ќ•ў•є•»•ї•й°Љ§»§§§®§–°Ґљљ ÷ЉЋ∞мґе° §Є§√§Џ§у§Ј§г§§§√§ѓ°Ћ§ќ°Ў≈м≥§∆ї√ж…®Ј™ћ”° §»§¶§Ђ§§§…§¶§Ѕ§е§¶§“§ґ§ѓ§к§≤°Ћ°ў§ј§ђ°Ґ§≥§ќљљ ÷ЉЋ∞мґејијЄ§ѕ§ §Ђ§ §Ђ§ќ√“Ј√Љ‘§«°Ґ∆…Љ‘•µ°Љ•”•є§в§™§µ§™§µ»і§Ђ§к§ §Ђ§√§њ°£
»а§ѕ°Ґ°Ў≈м≥§∆ї√ж…®Ј™ћ”°ў§ќ¬≥ ‘§«§Ґ§л°Ў¬≥…®Ј™ћ”°ў§ќЇ«љ™¬и£±£≤ ‘і©є‘§ќЅ∞°є«ѓ§ќ Єјѓ£≥«ѓ° £±£Є£≤£∞°ЋјµЈоі©є‘§ќ¬и£±£± ‘§т¬ё§Ћ∆ю§м§∆«д§кљ–§Ј§њ°£§љ§ќ¬ё§Ћ§ѕ°ҐЋ№§»∞мљп§Ћ≤ќјоєсƒз° §¶§њ§ђ§п§ѓ§Ћ§µ§ј°Ћ§ђ…Ѕ§§§њєЊЄЌµ»Єґ§ќЌЈљч§њ§Ѕ§ќ•÷•н•ё•§•…§ §й§ћ∞мЋз≥®§т…’ѕњ§Ћ…’§±§њ§ќ§«§Ґ§л° њё»«ї≤Њ»°Ћ°£
°°§љ§ќјќ°Ґ≥Ў«ѓї®їп§дћ°≤и§ќЈоі©їп§ќ…’ѕњ§т≥Џ§Ј§у§јµ≠≤±§ђ§Ґ§л э§в¬њ§§§≥§»§ј§н§¶§ђ°Ґ§≥§ќ°÷…’ѕњ°„§»§§§¶іл≤и§ѕ°Ґљљ ÷ЉЋ∞мґе§ђєЌ§®§њ§в§ќ§т”ећр° §≥§¶§Ј°Ћ§»§є§л°£

Ґ•љљ ÷ЉЋ∞мґе°Ў¬≥…®Ј™ћ”°ў£±£± ‘° Єјѓ£≥«ѓ°“£±£Є£≤£∞°”і©°Ћ§ќ…’ѕњ§ќєсƒз≤и§ќ∞мЋз≥®°£µ»Єґ§ќЌЈљч§ђњІЇю§к§«…Ѕ§Ђ§м§∆§™§к°Ґ°÷§§§н§§§н§ЋћЊ§ѕ —° §Ђ°Ћ§ѕ§м§…§вЉЏ° §Ђ°Ћ§к§∆§ѓ§л¬ј…„° §њ§ж§¶°Ћ§ѕ§™§ §Є«÷° §µ§Ђ§Ї§≠°Ћ§ќљкЇо°„§»љс§Ђ§м§∆§§§л°£
≤Ђ…љїж°ƒєЊЄЌЄеіь°Ґ∞¬± £і«ѓ° £±£Ј£Ј£µ°Ћ§Ђ§й Є≤љ£≥«ѓ° £±£Є£∞£ґ°ЋЇҐ§Ћ§Ђ§±§∆¬њњфі©є‘§µ§м§њЅрЅ–їж° §ѓ§µ§Њ§¶§Ј°Ћ°£ёѓЌо° §Ј§г§м°Ћ°Ґ≥кЈќ°Ґ…чї…§тњ•§кЄт§Љ§њ¬зњЌЄю§≠§ќ≥®∆ю§кЊЃјв°££±Їэ£µ√ъ° £±£∞•Џ°Љ•Є°Ћ§Ђ§йјЃ§к°Ґ£≤°Ґ£≥Їэ§«∞м…ф§»§Ј§њ°£¬е…љЇоЉ‘§Ћ§ѕ°Ґќшјољ’ƒЃ° §≥§§§Ђ§п§ѕ§л§ё§Ѕ°Ћ°Ґї≥≈мµю≈Ѕ° §µ§у§»§¶§≠§з§¶§«§у°Ћ°£
љљ ÷ЉЋ∞мґе°ƒ£±£Ј£ґ£µ°Ѕ£±£Є£≤£≤°£єЊЄЌЄеіь§ќµЇЇоЉ‘°£≈м≥§∆ї§тќє§є§лћпЉ°§µ§уіо¬њ§µ§у§ђ• •у•ї•у•є§ Њ–§§§т§ѓ§кє≠§≤§л≥кЈќЋ№° §≥§√§±§§§№§у°Ћ°Ў≈м≥§∆ї√ж…®Ј™ћ”°ў§ѕ°Ґљй ‘° µэѕ¬£≤«ѓ°“£±£Є£∞£≤°”°Ћ§Ђ§й»ђ ‘° Є≤љ£ґ«ѓ°“£±£Є£∞£є°”°Ћ§ё§«і©є‘§µ§м°Ґ¬≥ ‘§вЉ°°єљ–§µ§м§∆ Єјѓ£µ«ѓ° £±£Є£≤£≤°Ћ§ё§«¬≥§§§њ°£∞мґе§ѕ°Ґ≤Ђ…љїж°ҐёѓЌоЋ№° §Ј§г§м§№§у°Ћ°Ґ∆…Ћ№° §и§я§џ§у°Ћ°Ґ“фЋ№° §ѕ§ §Ј§№§у°Ћ§ §…°Ґ§µ§ё§ґ§ё§ •Є•г•у•л§Ћ¬њ§ѓ§ќЇо… §тїƒ§Ј§∆§§§л°£
≤ќјоєсƒз°ƒ£±£Ј£Є£ґ°Ѕ£±£Є£ґ£і°£єЊЄЌЄеіь§ќ…вј§≥®ї’°£ћтЉ‘їчій≥®§ќґ”≥®§»ЅрЅ–їж§ќЅё≥®§т∆ј∞’§»§Ј§њ°£ї∞ј§Ћ≠єс° §»§и§ѓ§Ћ°Ћ§тљ±ћЊ°£

ћо л°¶ƒћ
ЌоЄм°÷ћЏ«µ∞Ћ° •я•§•й°„Љи§к°„
Ї£§«§вЉг§§њЌ§њ§Ѕ§ѕ°÷KY°„° ґхµ§§т∆…§б§ §§°Ћ§»§§§¶§«§Ґ§н§¶§Ђ°£§љ§ќЊм§ќ Ј∞ѕµ§§дЊхґЈ»љ√«§ќ§«§≠§ §§°÷ћо л°„§ њЌ§т§µ§є°£
°° °÷§Ґ§§§ƒ§ѕћо л§ ≈џ§ј°„§ §…§»§§§¶§≥§»§ѕ°ҐЇ£§«§в§Ј§з§√§Ѕ§е§¶≤сѕ√§ќ§ §Ђ§«Љ™§Ћ§є§л°£
°° °÷ћо л°„§ѕЄј§п§Ї§в§ђ§ °Ґј§Њр°ҐњЌЊр§ќµ°»щ§тЌэ≤т§«§≠§ §§њЌ§т§µ§єЄјЌ’§«§Ґ§л°£§»§ѓ§Ћ√Ћљчі÷§ќ§≥§»§Ћ«џќЄ§ќ§≠§Ђ§ §§§и§¶§ њЌ§д°Ґ≈ƒЉЋ§ѓ§µ§ѓє‘∆∞§ §…§ђјцќэ§µ§м§∆§§§ §§њЌ§в§µ§єЄјЌ’§«°Ґ…‘њи° §÷§є§§°Ћ§»§в§§§¶°£
°° °÷ћо л°„§ѕ§в§Ѕ§н§у§Ґ§∆їъ§«°Ґ≤Ђ…љїж° §≠§”§з§¶§Ј°Ћ§Ћ°Ўћо л¬зњ√∆о≥‘ЌЈ° §д§№§ј§§§Є§у§ §у§Ђ§ѓ§Ґ§љ§”°Ћ°ў° ≈Јћј£і«ѓ°“£±£Ј£Є£і°”і©°Ћ§»§§§¶¬кћЊ§ќЇо… §ђ§Ґ§л§ѓ§й§§§«°Ґј§§ЋЄј§¶≈ƒЊ¬∞’Љ°§ќїю¬е° £±£Ј£ґ£Ј°Ѕ£Є£ґ°Ћ§Ћ§ѕєЊЄЌ§√ї“§њ§Ѕ§ѕ°Ґ°÷ћо 맻≤љ ™§ѕ»ҐЇђ§ќји§Ћ§Ј§Ђ§§§ §§°„§ §…§»∞≠¬÷§т§ƒ§§§∆°ҐєЊЄЌ§√ї“§Ћћо л§ Љ‘§ѕ§§§ §§§»ґѓƒі§Ј§∆§§§њ°£≈ЈћјЇҐ§Ћ°÷ћо л°„§ќїъ§т§Ґ§∆§л§ќ§ђ∞м»ћ≈™§Ћ§ §√§∆§≠§∆§§§њ§»єЌ§®§∆§и§Ђ§н§¶°£
°°°÷ћо л°„§ќЄмЄїјв§ѕ§§§ѓ§ƒ§Ђ§Ґ§л°£≈ƒЉЋЉ‘§ќ°÷ћо…„° §д§÷°Ћ°„§ђл¬° § §ё°Ћ§√§њ§»§§§¶јв§д°Ґћщ° ћщ§ѕји§ђЄЂ≈ѕ§ї§ §§§»§≥§н§ §ќ§«°ҐЅкЉк§ќ§≥§»§дїц¬÷§т§и§ѓЄЂ≈ѕ§ї§ §§§и§¶§ •ј•б§ ≈џ§ќ∞’ћ£°£…¬Њх§тЄЂƒћ§ї§ §§∞еЉ‘§ќ§≥§»§тйЃ∞еЉ‘§»§§§¶§ќ§»∆±§Є°Ћјв§«§Ґ§л°£
°° µ»Єґ§«µп¬≥§±§є§лЉг√ґ∆б§тЈё§®§Ћє‘§ѓ§ђ°Ґ√ѓ∞мњЌ§»§Ј§∆µҐ§√§∆§≥§ §ѓ§∆°Ґ•я•§•йЉи§к§ђ•я•§•й§Ћ§ §л»Є§ђЌоЄм§ќ°÷ћЏ«µ∞Ћ° •я•§•й°„Љи§к°„§«§Ґ§л°£§љ§≥§«≈ƒЉЋЉ‘§ќ»”њж§≠§«ћо л§ јґ¬Ґ° §ї§§§Њ§¶°Ћ§ §йЉг√ґ∆б§тѕҐ§м§∆µҐ§л§ј§н§¶§»Јё§®§Ћ§д§л§ђ°Ґ§≥§ќћо л§ јґ¬Ґ§в•я•§•й§Ћ§ §л°£§≥§м§ѕї≥≈мµю≈ЅЇо§ќёѓЌоЋ№°Ўµю≈ЅЌљїп°ў° і≤јѓ2«ѓ°“1790«ѓ°”§д≤Ђ…љїж°Ў≤љ ™ѕ¬Ћ№Ѕр° §д§ё§»§џ§у§Њ§¶§Ј°Ћ°ў° ∆±10«ѓі©°Ћ§ЋЄґѕ√§ђЄЂ§®°Ґ≈ƒЉЋЉ‘§ќ¬ећЊїм§ђћо 맫§в§Ґ§√§њ°£
§§§Ї§м§Ћ§ї§и°Ґ°÷ћо л°„§»§§§¶Єм§ѕЌЈќ§µ»Єґ§ђ»ѓјЄЄї§ј§√§њ§и§¶§«§Ґ§л°£≤Ђ…љїж°ЎƒћњЌ° §ƒ§¶§Є§у°Ћ§§§н§ѕ§њ§у§Ђ°ў° ≈Јћј£≥«ѓі©°Ћ° њё»«ї≤Њ»°Ћ§Ћ§ѕ°ҐЌЈ≥«§«ћо л§ђЅы§Ѓљ–§єЊмћћ§ђ§Ґ§л°£
°° ћо л§ќ»њ¬–§ђ°÷ƒћ°„§«°Ґ°÷§Ґ§ќњЌ§ѕ°Ґ§ §Ђ§ §Ђ≤ќ…сімƒћ§ј§Ќ°„§»§§§¶…ч§ЋЄљ¬е§«§вЄј§¶°£ ™їц§Ћ§и§ѓƒћґ«° §ƒ§¶§Ѓ§з§¶°Ћ§Ј§∆§§§л§≥§»§д°Ґ§љ§у§ њЌ§тїЎ§Ј§∆Єј§¶ЄјЌ’§«§Ґ§л°£§≥§ќ°÷ƒћ°„§в°÷ћо л°„§»їч§∆°Ґ≤÷ћш≥¶§ §…§ќїцЊр§дЌЈ§”§Ћ§ѓ§п§Ј§Ђ§√§њ§к°Ґ§љ§≥§«јЄ≥и§є§лњЌ° ЌЈљч§дЈЁЉ‘§ §…°Ћ§ќњЌЊр§т§и§ѓњі∆ј§њ§≥§»§т§§§¶ЄјЌ’§ј§√§њ°£§»§ѓ§Ћ§љ§у§ њЌ§ќ§≥§»§тїЎ§Ј§∆°÷ƒћњЌ°„§»§вЄј§¶§Ј°Ґ°÷ƒћ§кЉ‘°„§»§вЄј§√§њ°£
°° °÷ƒћњЌ°„§»°÷ƒћ§кЉ‘°„§«§ѕ°Ґ°÷ƒћ§кЉ‘°„§ќ§џ§¶§ђЄјЌ’§ќјЃќ©§»§Ј§∆§ѕЅб§ѓ°ҐєЊЄЌїю¬е§вљйіьЇҐ§ќ£±£ґ£µ£∞«ѓ¬е§Ћ§ѕ§є§«§Ћї»§п§мљ–§Ј§∆§§§њ§и§¶§«°Ґ°÷ƒћњЌ°„§ѕћјѕ¬іь° £±£Ј£ґ£і°Ѕ£Ј£±°Ћ§Ћµ»Єґ§«јЄ§ё§м§њЄм§«°Ґ∆±їю§Ћ°÷¬зƒћ°„§»§§§¶ЄјЌ’§вћјѕ¬£ґ°Ґ£Ј«ѓЇҐ§Ђ§йќЃє‘§Ј§ј§Ј°Ґ≈ƒЊ¬їю¬е§Ћјє§у§Ћї»§п§м§њЄм§ќ§и§¶§ј§√§њ§ђ°Ґ£≤£∞«ѓ§џ§…§ќјЄћњ§«≈Јћј£Ј«ѓЇҐ§Ћ§ѕ«—° §є§њ°Ћ§к§ј§Ј§њ°£
°° °÷¬зƒћ°„§тї»§√§њЄм§Ћ°÷љљ»ђ¬зƒћ°„§»§§§¶Єм§ђ§Ґ§л°£ї•Їє° ¬Ґљ…°Ћ§д∆ьЋ№ґґЊЃ≈ƒЄґƒЃ§Ґ§њ§к§ќµыћд≤∞§ќ√ґ∆бљ∞§њ§Ѕ§ќ§≥§»§«°ҐєЊЄЌ§ќЌЈ§”њЌ•ў•є•»£±£Є§тЄј§√§њЄм§«§в§Ґ§л§ђ°Ґ≈ƒЊ¬їю¬е§ќє•Ј µ§§»§§§¶§Ђ°Ґ•–•÷•лЈ µ§§ќљ™я᧻§»§в§Ћ°÷љљ»ђ¬зƒћ°„§»§§§¶ЄјЌ’§вЊ√§®§њ°£
°÷¬зƒћ°„§ђ§Ґ§м§–°÷ЊЃƒћ°„§ђ§Ґ§√§∆§в§§§§§п§±§«°Ґ°÷ЊЃƒћ°„§ѕ°÷¬зƒћ°„§Ћ»ж≥”§Ј§∆°Ґћ§љѕ§ «ѓЉг§§Љ‘§тїЎ§Ј°Ґ§Ґ§ё§кЌЈ§”§Ћґв§т§Ђ§±§ §§Љ‘° §Ђ§±§й§м§ §§Љ‘°Ћ§тїЎ§єЄјЌ’§«§Ґ§√§њ°£
°°°÷¬зƒћ°„§ѕЊ¶«д§«Їв§тјЃ§Ј°Ґґв§Ћїећ№§т§ƒ§±§Їєлј™§ЋЌЈ§÷¬зґвїэ§Ѕ§ј§√§њ§»§є§л§»°Ґ°÷ЊЃƒћ°„§ѕ§µ§Ј§Ї§б°ҐЇ£∆ь§«§§§®§–£…£‘їЇґ»§ќЉгЉк§ќЈ–±ƒЉ‘§д•”•√•»•≥•§•у§ §…§ќ≤ЊЅџƒћ≤я° ∞≈єжƒћ≤я°Ћ§ §…§«°Ґґвћў§±§ќ§њ§б§Ћ≈кїс§ѕ§є§л§±§м§…°ҐЌЈ§”§Ћ¬з√ј§ їґЇв§ѕ§Ј§ §§°Ґ§Ѕ§з§√§»§Ј§њЌЈ§”њЌ§»§§§√§њ§»§≥§н§«§Ґ§н§¶§Ђ°£≤њљљ≤ѓ±я§»§§§¶њ»Ѕђ§тјЏ§√§∆єлЌЈ§Ј°Ґ∞мј§§т…ч󔧺§л§и§¶§ °÷¬зƒћ°„§ђЄљ§м§∆°Ґ•≥•н• •¶•§•л•є§тњб§√»ф§–§Ј§∆§в§й§§§њ§§§»§≥§н§«§Ґ§л°£
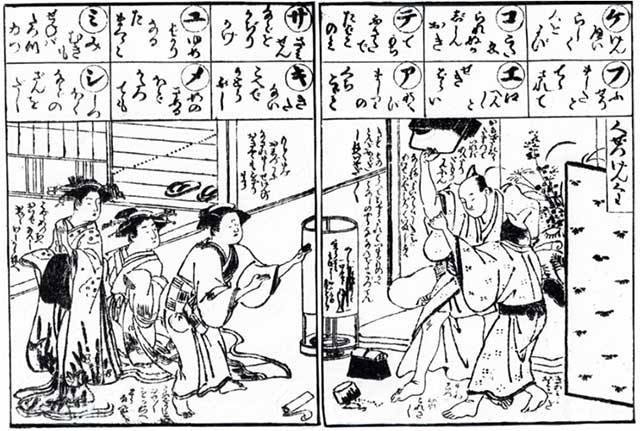
Ґ•ЌЈљч≤∞§«§ќ°÷ЄэјвЈц≤ё° §ѓ§Љ§ƒ§≤§у§Ђ°Ћ°„§ќЊмћћ°£§њ§–§≥Ћя§тњґ§кЊе§≤§∆≈№§лћо л§ µ“§т°ҐЌЈљч≤∞§ќњЌ§њ§Ѕ§ђїя§б§Ћ∆ю§√§∆§§§л§»§≥§н°£•’•у§»Єј§√§∆∆®§≤љ–§єЌЈљч° ЇЄ°Ћ°ЎƒћњЌ§§§н§ѕ§њ§у§Ђ°ў° ≈Јћј£≥«ѓ°“£±£Ј£Є£≥°”і©°Ћ§и§к°£
≤Ђ…љїж°ƒ∞¬± £і«ѓ° £±£Ј£Ј£µ°Ћ°Ѕ Є≤љ£≥«ѓ° £±£Є£∞£ґ°Ћ§ё§«і©є‘§µ§м§њ≥®∆ю§к§ќ∆…§я ™°£¬зњЌ§ќ•ё•у•ђ°¶•≥•я•√•ѓ§»§§§√§њ∆вЌ∆§«°Ґ…љїж§ђ≤ЂњІ§«§Ґ§√§њ§»§≥§н§Ђ§й§ќЄ∆Њќ°£
≈ƒЊ¬∞’Љ°°ƒєЊЄЌ√ж°¶Єеіь§ќЋлјѓ≤»§«Ѕкќ…»Ќ§ќ»ЌЉз°£¬и£є¬еЊ≠Ј≥∆Ѕјо≤»љ≈§»£±£∞¬еЊ≠Ј≥≤»Љ£§ќњЃ«§§т∆ј§∆ЊЃјЂ§Ђ§й¬зћЊ°ҐѕЈ√ж§Ћќ©њ»°ҐЊ¶ґ»їсЋ№§ќ≥иЌ—§Ћ§и§лњ£їЇґљґ»јѓЇц§»њЈ≈ƒ°¶єџї≥≥Ђ»ѓ°Ґ≥∞єсЋ«∞„§тњдњ §є§лј—ґЋЇвјѓјѓЇц§т§™§≥§ §¶§ђ°Ґ¬з±ь§д…рїќ≥ђµй§Ћ§в»њ»ѓ§тЊЈ§≠≤№∞–√ѕ≥Ђ»ѓ§ §…§ќЈ„Їц§ќ≈”√槫ЉЇµ”§є§л°£§љ§ќјѓЇцњдњ їю¬е§т°÷≈ƒЊ¬їю¬е°„§»§§§¶°£

√ЉЄб§ќјбґз
°°£µЈо£µ∆ь§ќ§≥§»§т°ҐґбЇҐ§«§ѕ°ҐОҐ√ЉЄб° §њ§у§і°Ћ§ќјбґзО£§»§§§¶Єј§§ э§ѕ§Ґ§ё§к§ї§Ї°Ґ§в§√§—§йОҐї“§…§в§ќ∆ьО£§»Є∆§÷§и§¶§Ћ§ §√§њ°£ °°§љ§в§љ§в√ЉЄб§ќјбґз§»§ѕ°Ґ√жєс§ќћс І° §д§ѓ§ѕ§й°Ћ§§§ќє‘їц§ђ∆ьЋ№§Ћ≈ѕЌи§Ј°Ґ¬з≤љ§ќ≤юњЈ° £ґ£і£µ°Ћ∞ Єе§Ћ£µЈо£µ∆ь§ќє‘їц§Ћƒк§б§й§м°ҐЄЃји§ЋЊ‘≥ч° §Ј§з§¶§÷°Ћ§дЋ©° §и§в§Ѓ°Ћ§т≥Ё§±§∆Љўµ§§т§ѕ§й§¶…чљђ§Ћ§ §√§њ§»§§§¶§Ђ§й°ҐќтїЋ§ќ§Ґ§л«ѓ√жє‘їц§«§Ґ§л°£єЊЄЌїю¬е§Ћ§ §кµ№√жє‘їц§»§Ј§∆§ѕі Ѕ«≤љ§µ§м§њ§ђ°Ґ§§§√§—§уљоћ±§ќ§Ґ§§§ј§«јє§у§Ћ§ §√§њ§и§¶§«§Ґ§л°£
°°
°°єЊЄЌїю¬е§Ћ§ §√§∆»Њј§µ™ґб§ѓ§ќЈƒ∞¬Єµ«ѓ° £±£ґ£і£Є°Ћ°Ґ§≥§ќјбґз§ЋЊю§лє√° §Ђ§÷§»°Ћ§ќєл≤Џ§ ўѕ° §≥§Ј§й°Ћ§®§тґЎїя§є§лƒЃњ®° §ё§Ѕ§÷°Ћ§м§ђљ–§µ§м§њ°£ґвїе°¶ґдїе§дЌьї“√ѕ° § §Ј§Є°£§¶§л§Ј≈…§к§Ћґвґд§ќ іЋц§«…Ѕ§ѓЉђ≥®°“§ё§≠§®°”°Ћ§Ћ§Ј§∆§ѕ§ §й§ §§§»§ќњ®§м§«§Ґ§л°£§≥§ќ§≥§»§Ђ§йќ©«…§ є√њЌЈЅ§т§Ґ§ƒ§й§®§л≤»§в§Ґ§√§њ§≥§»§ђ§¶§Ђ§ђ§п§м§л°£ °° §≥§ќƒЃњ®§м§Ћ§ѕ°Ґє√§тЊю§л§»∆±їю§Ћ°ҐЄЃји§ЋЊю§лЊбсƒ° §Ј§з§¶§≠°Ћ§д…рЉ‘°ҐЄс° §≥§§°Ћ§ §…§т…Ѕ§§§њЊЃіъ° Ї£§ќ§и§¶§ њб§≠ќЃ§Ј§«§ѕ§ §§°Ћ§ѕ°ҐЄ®јљ§«§ѕ§ §ѓ…џ§ЂћЏћ §Ћ§є§л§и§¶§Ћ§»§Ґ§л°£§ё§њ°Ґєл≤Џ§«§ §§є√њЌЈЅ§ §й£≤°Ґ£≥¬ќ§тЊю§√§∆§в§и§н§Ј§§§»љс§Ђ§м§∆§§§л°£
°°
°°ЊЉѕ¬£≥£∞«ѓ¬е∞ Ѕ∞§ќјЄ§ё§м§ќј§¬е§Ћ§ѕ°Ґ√ЉЄб§ќјбґз§»§§§®§–°Ґ«рћя° §Ђ§Ј§п§в§Ѕ°Ћ§ддр° §Ѕ§ё§≠°Ћ§тњ©§ў°Ґ∆ЄЌЎ°÷§ї§§§ѓ§й§ў°„§дОҐ§≥§§§ќ§№§кО£§т≤ќ§√§њ§≥§»§д°Ґјƒґх§тЅ‘і—§Ћ±Ћ§∞°÷Єс§ќ§№§к°„§тї„§§љ–§є§а§≠§в§™§™§Ђ§н§¶°£ћл§ѕЊ‘≥ч≈т§Ћ∆юЌб§Ј§њµ≠≤±§в§Ґ§л§ј§н§¶§ђ°ҐєЊЄЌїю¬е§ѕЌв∆ь§ќ6∆ь§ЋЅђ≈т§«Њ‘≥ч≈т§Ћњї° §ƒ°Ћ§Ђ§л§ќ§ђљоћ±§ќ≥Џ§Ј§я§«§Ґ§√§њ°£
°°°÷Єс§ќ§№§к°„§ѕ…р≤»§ќ…чљђ§»§§§п§м§л§ђ°ҐєЊЄЌїю¬е√жіь§ё§«§ќїсќЅ§Ћ§ѕ°Ґ§љ§ќ≥®§ѕ§ §Ђ§ §ЂЄЂ§ƒ§Ђ§й§ §§°£ЋлЋц§Ђ§йћјЉ£§Ћ§ §л§»°ҐЄљ¬е§ќ§и§¶§ њб§≠ќЃ§Ј§ќЄс§ќ§№§к§ђ¬њ§ѓ§ §л°£є≠љ≈° §“§н§Ј§≤°Ћ§ќ°÷ћЊљкєЊЄЌ…іЈ °„§Ћ§ѕґх§Ћ±Ћ§∞¬з§≠§ Єс§ќ§№§к§ђ…Ѕ§Ђ§м§∆§™§к°ҐћјЉ£§ќ ЄЄ•§Ћ§ѕ°Ґї∞±џ•«•—°Љ•»§ќ≤∞Ње§«Њю§й§м§њ§ §…§»ЄЂ§®§л°£њбќЃ§Ј•є•њ•§•л§ќЄс§ќ§№§к§ѕ°Ґ∞∆≥∞њЈ§Ј§§°£
°°
µ’§Ћ°Ґ§а§Ђ§Ј√ЉЄб§ќјбґз§Ћє‘§п§м§∆§§§њ§ђ°ҐЇ£§«§ѕ§є§√§Ђ§к§є§њ§√§∆§Ј§ё§√§њ§≥§»§ђ§Ґ§л°£ °°§≥§ќ∆ь°ҐЉгЉ‘§њ§Ѕ§ђ°÷џр≈Ј° §№§у§∆§у°Ћ°„§»§§§¶±пµѓ ™§т√і§§§«≥є√ж§тќэ§к ⧧§њ…чљђ§«§Ґ§л°£џр≈Ј§»§ѕ°ҐЇўƒє§§їж “§д…џ§«Єс§ќЈЅ§т§ƒ§ѓ§√§њ Њ¬Ђ° §Ў§§§љ§ѓ°Ћ§тЋј§ќји§ќѕќ¬Ђ°“§п§й§њ§–°”§Ўї…§Ј§њ§в§ќ§«°ҐЉгЉ‘§њ§Ѕ§ѕјо§«њеє§ќ•° §я§Ї§і§к°Ћ§т§Ј§∆§Ђ§й°Ґ§≥§м§т√і§§§« ⧧§∆≤у§√§њ°£§љ§Ј§∆°Ґћс І§§§ќ§™Љц° §ё§Є§ °Ћ§§§Ћ§≥§ќ Њ¬Ђ§т«д§к°Ґї»§§§™§п§√§њџр≈Ј§ќЋј§ѕјо§ў§к§ §…§Ћї…§Ј§∆ію§∆§њ°£і≤јѓЄµ«ѓ° £±£Ј£Є£є°Ћ£іЈо§Ћ§ѕ°Ґ¬з§≠§ џр≈Ј§т¬зј™§«√і§§§«ќэ§к в§ѓ§≥§»§тЉЂљЌ§є§л§и§¶§Ћ§»§ќƒЃњ®§м§ђљ–§∆§§§л°£џр≈Ј§ќ∞мє‘§Ђ§й±пµѓ ™§ќ Њ¬Ђ§тµб§б§њњЌ§в§™§™§Ђ§√§њ°£
°°§≥§ќ…чљђ§ѕ°ҐћјЉ£§Ћ§ §√§∆§в≈мµю§«§ѕє‘§п§м§∆§§§њ§ђ°ҐЉЂЅ≥Њ√ћ«§Ј§∆§Ј§ё§√§њ§и§¶§ј°£
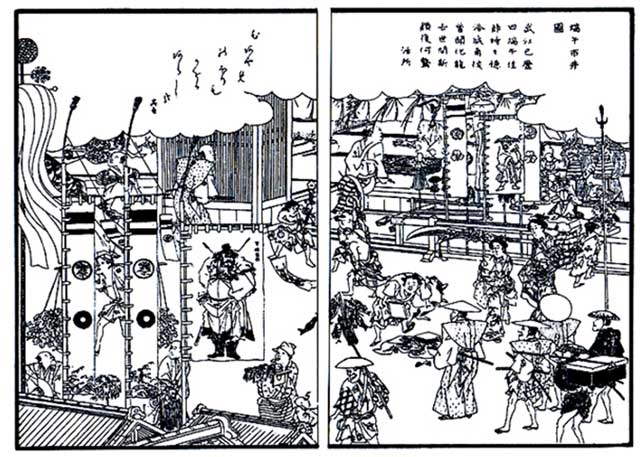
Ґ•≈Ј Ё£є«ѓ° £±£Є£≥£Є°Ћі©§ќ°Ў≈м≈‘Ї–їцµ≠° §»§¶§»§µ§§§Є§≠°Ћ°ў§Ћ…Ѕ§Ђ§м§њ°ҐєЊЄЌ§ќ√ЉЄб§ќјбґз§ќ…чЈ °£∆ї§Ћ§ѕ°ҐЊбсƒЌЌ§ќ§ќ§№§к°Ґ≤»ћж§тјч§б§њіъ°ҐЄс§ќ§№§к§дњбќЃ§Ј§ђ§ѕ§њ§б§≠°Ґ≈є§Ћ§ѕ°Ґє√§т§ѕ§Є§б…рЉ‘њЌЈЅ§ђ ¬§ў§й§м§∆§§§л°£√ж±ыЉкЅ∞§ќ≥ё§т»п§√§њњЌ ™§ђЇЄЄ™§Ћ√і§§§«§§§л§ќ§ђ°÷џр≈Ј°„°£Єс§ќЈЅ§т§Ј§њ Њ¬Ђ§ђ§њ§ѓ§µ§уї…§µ§√§∆§§§л°£§Ѕ§ё§≠§тЄ™§Ћ§ќ§ї§њњЌ§ђ¬≥§ѓ°£…рїќ§ќ∞мє‘§ќЅ∞§«°Ґї»§§§ќї“§…§в§ђ«рћя§тЌо§»§Ј§∆§Ј§ё§√§њ°£√ж±ы§ќї“§…§в§њ§Ѕ§ѕ°ҐЊ‘≥ч¬«° Њ‘≥ч§т¬Ђ§Ќ§њ∆м§т√ѕћћ§Ћ√°§≠§ƒ§±≤ї§ќ¬з§≠§µ§тґ•§¶°Ћ°Ґ∞х√ѕ¬«° §§§у§Є§¶§Ѕ°£ј–≈к§≤єзјп°ЋЌЈ§”§Ћґљ§Є§∆§§§л°£
°÷ћЊљкєЊЄЌ…іЈ °„°ƒ∞¬јѓ£≥«ѓ° £±£Є£µ£ґ°Ћ§Ђ§й∆±£µ«ѓ§Ћ§Ђ§±§∆љ–»«§µ§м§њ°Ґ≤ќјоє≠љ≈° £±£Ј£є£Ј°Ѕ£±£Є£µ£Є°ЋЇ«»’«ѓ§ќ…чЈ »«≤и•Ј•к°Љ•Ї°£єЊЄЌћЊљк§т£±£±£єЋз§ќ≥®§«Њ“≤р§Ј§∆§§§л°£
љй≥п
°°љй≥п° §ѕ§ƒ§ђ§ƒ§™°Ћ§» є§±§–°Ґї≥ЄэЅ«∆≤° §љ§…§¶°Ћ§ќґз°÷ћ№§Ћ§ѕјƒЌ’ї≥їюƒї° §д§ё§џ§»§»§Ѓ§є°Ћљй≥п°„° ±д х£ґ«ѓ°“£±£ґ£Ј£Є°”°Ћ§тї„§§љ–§єњЌ§в§™§™§Ђ§н§¶°£є√»еєс° §Ђ§§§ќ§ѓ§Ћ°Ґї≥ЌьЄ©°Ћ§Ђ§йєЊЄЌ§Ўљ–§∆§≠§∆ЊЊ»ш«ќЊ÷° §–§Ј§з§¶°Ћ§ §…§»њ∆Єт§тЈл§у§ј«–њЌ°¶Ѕ«∆≤§ђ°ҐєЊЄЌњЌ§њ§Ѕ§ђљй≥п§тƒЅљ≈Њёћ£§є§лљй≤∆§ќ…ч ™§т±”° §и°Ћ§у§ј§в§ќ§«§Ґ§л°£
°°
°÷љй ™° §ѕ§ƒ§в§ќ°Ћ§тњ©§®§–ЉЈљљЄё∆ьƒєјЄ§≠§є§л°„§»§§§¶¬ѓјв§ѕ°ҐєЊЄЌ§–§Ђ§к§«§ §ѓ¬зЇд§«§вЄј§п§м§∆§§§њ§и§¶§ј§ђ°Ґ§»§ѓ§ЋєЊЄЌ§«§ѕљй≥п§тƒЅљ≈§є§л§»§≥§н§Ђ§й°Ґљй ™§»§§§®§–љй≥п§т§µ§Ј§∆§§§њ§»Єј§√§∆§в§§§§§ј§н§¶°£єЊЄЌњЌ§ѕ°Ґјоћш§Ћ°÷ є§§§њ§Ђ є§§§њљй≥п°„§»§Ґ§л§ќ§ѕ°Ґїюƒї§ќљй≤ї° §ѕ§ƒ§Ќ°Ћ§»љй≥п§ќљй√Ќ° §ѕ§ƒ§Ќ°Ћ§т є§§§њ§Ђ§»°ҐєЊЄЌ§√ї“§њ§Ѕ§ќґљћ£§ѕ§љ§≥§Ћ§Ґ§√§њ§»§§§¶§≥§»§«§Ґ§л°£
≥щЅ“≤≠§дЊЃ≈ƒЄґ≤≠§«≥Ќ§м§њљй≥п§ѕ°Ґµё§ЃєЊЄЌ§Ў±њ§–§м§∆єв≤Ѕ§««д§й§м§њ°£Ѕ«∆≤§ќґз§ђјЄ§ё§м§∆§Ђ§й§џ§№£±ј§µ™Єе§Ћ§Ґ§њ§л≈Јћј«ѓі÷° £±£Ј£Є£±°Ѕ£Є£Є°Ћ°Ґј–ƒЃ° §≥§ѓ§Ѕ§з§¶°Ґ≈мµю≈‘√ж±ыґи°Ћ§ќ§µ§лґвїэ§Ѕ§ѕ°Ґљй≥п£±Ћ№§т£≤ќЊ£≤ ђ° ЄљЇя§ќ≤Ѕ≥ §Ћ§є§л§»ћу£≥£µЋь±яЅ∞Єе°Ћ§««г§§µб§б§њ§»°Ґї≥≈мµюї≥° §µ§у§»§¶§≠§з§¶§ґ§у°Ћ§ѕњп…Ѓ°Ў√Ўйбїеіђ° §ѓ§в§ќ§§§»§ё§≠) °ў§«≈Ѕ§®§∆§§§л°£
°° Єљ¬е§ќ•∞•л•б§«§ѕ°Ґ≥п§дЋо° §ё§∞§н°Ћ§ §…§ќ√жЌо§Ѕ° єь§Ћ§ƒ§§§њњ»°Ћ§ѕїй§ђ§ќ§√§∆»юћ£§ј§»ƒЅљ≈§є§л§ђ°ҐєЊЄЌ§√ї“§ѕµы§ќ√жЌо§Ѕ§ §…§ѕњ©§ў§ §Ђ§√§њ°£µюї≥§ќЈї°¶ї≥≈мµю≈Ѕ° §≠§з§¶§«§у°Ћ§ѕ°ҐёѓЌоЋ№° §Ј§г§м§№§у°Ћ°ЎЅндб° §љ§¶§ё§ђ§≠°Ћ°ў° ≈Јћј£Ј«ѓ°“£±£Ј£Є£Ј°”і©°Ћ§«°Ґ°÷ґв§ќтѕ° §Ј§г§Ѕ§џ§≥°Ћ§т§Ћ§й§яњј≈ƒЊење° §Є§з§¶§є§§°Ћ§«їЇ≈т° §¶§÷§ж°Ћ§т§ƒ§Ђ§√§њєЊЄЌ§√ї“§ѕ°Ґґщ≈ƒјо§«≥Ќ§м§л«тµы§ќ√жЌо§Ѕ§«§µ§®њ©§ў§ §§§»ЉЂЋэ§Ј§∆§§§л°„§»љс§§§∆§§§л°£
°°
§љ§у§ єЊЄЌ§Ћ¬–§Ј§∆°Ґ¬зЇд§ѕЉ¬Ќш§т§»§л…ч≈Џ§«§Ґ§√§њ§ђ°Ґљй ™§Ћ§ƒ§§§∆§ѕЊѓ§Ј§≥§ј§п§√§∆§§§њ§и§¶§«§Ґ§л°£
°° ∞жЄґјЊƒб° §µ§§§Ђ§ѓ°Ћ§ќ°Ў∆ьЋ№± ¬е¬Ґ° §Ћ§√§Ё§у§®§§§њ§§§∞§й°Ћ°ў° ЄµѕљЄµ«ѓ°“£±£ґ£Є£Є°”і©°Ґіђ∆у•ќ∞м°÷ј§≥¶§ќЉЏ≤∞¬зЊ≠°„°Ћ§Ћ§ѕ°Ґ§≥§у§ ѕ√§ђ§Ґ§л°£ £±§ƒ§«£≤ Є° §в§у°Ћ°Ґ£≤§ƒ§«£≥ Є§»°Ґљй≤Ўї“° §ѕ§ƒ§ §є§”°Ћ§т«д§к§ЋЌи§њ°££≤§ƒ§«£≥ Є§ќ§џ§¶§ђ∆ј§ј§»Єј§√§∆≥І§ђ«г§¶§ђ°Ґ§љ§≥§ќЉзњЌ∆£ї‘(§’§Є§§§Ѕ)§ѕ£±§ƒ§«£≤ Є§ќ§џ§¶§т«г§√§њ°£§љ§ќЌэЌ≥§ѕ°ҐЇ«јєіь§Ћ§ §м§–≤Ўї“§ѕ¬з§≠§ѓ§ §к°Ґ£±§ƒ£± Є§««г§®§л§и§¶§Ћ§ §л°£∆±§Є£≤§ƒ§«£≥ Є§«§в°ҐЇ«јєіь§Ћ§ѕ¬з§≠§ §в§ќ§Ћ§ §л§Ђ§й∆ј§ј§»§§§¶§п§±§«§Ґ§л°£§≥§у§ ≈∞ƒм§Ј§њєзЌэЉзµЅ§ќїѕЋц≤∞§«§Ґ§л¬зЇењЌ§ѕ°ҐєЊЄЌ§√ї“§џ§…љй ™§Ћ§≥§ј§п§й§ §§°£
°°§»§≥§н§«°Ґµюї≥§ђ°Ґљй≥п£±Ћ№§т£≤ќЊ£≤ ђ§««г§√§њњЌ§ђ§§§њ§»§§§¶ѕ√§т…гњ∆§Ћ§є§л§»°Ґ≥пє•§≠§ќ…гњ∆§ѕ°Ґљ©§ќЇ«јєіь§Ћ§ §м§–¬з§÷§к§ §в§ќ§ђ£≤…і Є° ≈цїю§ќЅкЊм§«§§§®§–°Ґ£≤ќЊ£≤ ђ§ќћу60 ђ§ќ£±Ѕк≈ц°бћу6000±я§ѓ§й§§°Ћ§ §ќ§Ћ§»√≤¬©§Ј§њ§»§§§¶°£
°°
ЋлЋц§Ћ§ѕґвїэ§Ѕ§њ§Ѕ§ѕ§є§«§ЋќнЌо§Ј°Ґљй≥п§т£≤…і Є§««г§¶Љ‘§ѕ§§§ §§їюјб§Ћ§ §√§њ§»°Ґµюї≥§ѕљс§§§∆§§§л°£ћјЉ£∞ЁњЈ§тЅ∞§Ћ°Ґм‘¬ф§тЄј§®§ §§…‘Ј µ§§»§ §√§∆°ҐєЊЄЌ§√ї“µ§ЉЅ§ђЊ√§®§Ђ§±§∆§§§њ°£
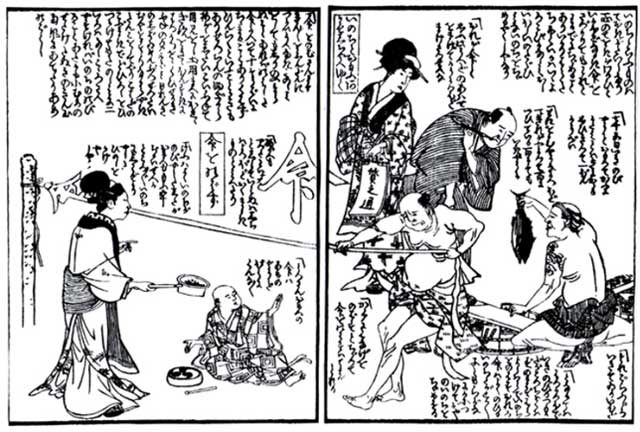
Ґ•±¶§ќ≥п«д§к§Ђ§йљй≥п§т«г§™§¶§»§Ј§∆§§§лƒвЉз§ѕ°Ґєв√Ќ§ј§»Єј§§§ §ђ§й§вЉЈљљЄё∆ьƒєјЄ§≠§є§л§њ§б§Ћ°ҐљчЋЉ§ќ∞Ѕ° §Ґ§п§ї°Ћ§ќ√е ™§тЉЅ§Ћ∆ю§м§л§»§§§¶°£љчЋЉ§ќЉк§Ћ§ѕЉЅ≤∞§ќƒћ§§ƒҐ§ђ°£§љ§ќЉкЅ∞§«ћњ§ќЋј§т§ќ§–§љ§¶§»Јьћњ§Ћ§ §√§∆§§§л§ќ§ѕ°Ґќў≤»§ќƒвЉз°£љчЋЉ§ѕ≤–§ќ§Ј° Ї£§ќ•Ґ•§•н•у°Ћ§«ћњ§ќ§Ј§п§т§ќ§–§љ§¶§»§Ј§∆§§§л°£° ї≥≈мµю≈Ѕ°ЎЄжл–јчƒєЉчЊЃћж° §™§у§Ґ§ƒ§й§®§Њ§б§Ѕ§з§¶§Є§е§≥§в§у°Ћ°ўµэѕ¬£≤«ѓ°“£±£Є£∞£≤°”і©°Ґ≈мµю≈‘ќ©√ж±ыњёљсіџ≤√≤м ЄЄЋ¬Ґ°Ћ
ї≥ЄэЅ«∆≤°ƒ£±£ґ£і£≤°Ѕ£±£Ј£±£ґ°£єЊЄЌЅ∞іь§ќ«–њЌ°£єЊЄЌ§Ћљ–§∆іЅ≥Ў§тљ§§б°Ґ∞мїю°Ґµю§Ћ§ќ§№§кѕ¬≤ќ°Ґљс°Ґ«–ля§т≥Ў§÷°£»’«ѓ§ѕ≥лЊю§Ћљї§у§ј°£
ї≥≈мµюї≥°ƒ£±£Ј£ґ£є°Ѕ£±£Є£µ£Є°£єЊЄЌЄеіь§ќµЇЇоЉ‘° §≤§µ§ѓ§Ј§г°Ћ°£ї≥≈мµю≈Ѕ§ќƒп°£дњєп° §∆§у§≥§ѓ°Ћ§т§ §к§п§§§»§Ј§њ°£∆…Ћ№° §и§я§џ§у°Ћ§дєзіђ° §і§¶§Ђ§у°Ћ§вљс§§§њ°£
ї≥≈мµю≈Ѕ°ƒ£±£Ј£ґ£±°Ѕ£±£Є£±£ґ°£єЊЄЌЄеіь§ќµЇЇоЉ‘°Ґ…вј§≥®ї’°£≤Ђ…љїж° §≠§”§з§¶§Ј°Ћ°ҐёѓЌоЋ№§ќ¬и∞мњЌЉ‘§»§Ј§∆≥ићц§є§л§ђ°Ґі≤јѓ§ќ≤ю≥„§«…Ѓ≤“§ќ§ќ§Ѕ§ѕ°Ґ∆…Ћ№§дєЌЊЏњп…Ѓ§Ћ≈Њ§Є§њ°£
ёѓЌоЋ№°ƒЌЈќ§§«§ќ√Ћљч§ќ≤сѕ√§т§њ§ѓ§я§Ћ…Ѕ§§§њ°ҐєЊЄЌµЇЇо§ќ¬е…љ≈™§ √ї ‘ЊЃјв°£ї≥≈мµю≈Ѕ§ќ°ЎЅндб°ў§ѕ°ҐЌЈќ§§т§б§∞§лЇ«њЈ§ќѕ√¬к§дќЃє‘§т°ҐЉ¬Їя§ќњЌ ™§т•в•«•л§Ћ§Ј§∆ЉћЉ¬≈™§Ћ…Ѕ§§§њ§в§ќ°£
§™§Ў§љ§ђ√г§т ®§Ђ§є
°° њЈ√г§ќ»юћ£§Ј§§µ®јб§ѕ§в§¶§є§∞§«§Ґ§л°£
°°§™√г§ђЄљ¬е§ќ§и§¶§Ћµ§ЈЏ§Ћ∞ы§б§л§и§¶§Ћ§ §√§њ§ќ§ѕєЊЄЌїю¬е§Ћ§ §√§∆§Ђ§й§«§Ґ§л°£§љ§Ј§∆§™√г§ђљоћ±§ќ∞ы§я ™§Ћ§ §√§њєЊЄЌ√жіь∞ єя°Ґ§µ§ё§ґ§ё§ °÷√г°„§Ћ§ё§ƒ§п§лЄјЌ’§в»ѓјЄ§Ј§∆§ж§ѓ°£
°°§љ§м§ѕµу§≤§л§»•≠•к§ђ§ §§§џ§…§«§Ґ§л§ђ°Ґ°÷§™√г§ќї“§µ§§§µ§§°„° і √±§Ћ§«§≠§л°Ћ°÷§™√г§т§Ћ§і§є°„° §і§ё§Ђ§є°Ћ°÷√г§Ћ§є§л°„° «ѕЉѓ§Ћ§є§л°Ћ°÷√г»÷°„(√г»÷ґЄЄј°Ґ√г»÷Ја§ќќђ°£ЄЂ§®§є§§§њ§≥§»°Ћ§ §…§ѕ∆ьЊп≈™§ЋЇ£§«§вї»§п§м§∆§§§лЄјЌ’§«§Ґ§л°£
°° § §Ђ§«§в°Ґ°÷§™§Ў§љ§ђ√г§т ®° §п°Ћ§Ђ§є°„§»§§§¶ЄјЌ’§ѕ°ҐєЊЄЌ§ќњЌ§”§»§ђ¬зє•§≠§«°Ґ§µ§ё§ґ§ё§ ЄЈЁЇо… §Ћ≈–Њм§є§л°£§Ѕ§з§√§»ЈЏ ќ§Ј§њ§и§¶§ •Ћ•е•Ґ•у•є§тіё§я°Ґ§™§Ђ§Ј§ѓ§∆§њ§ё§й§ §§§≥§»§ќЈЅЌ∆§»§Ј§∆Єј§¶ЄјЌ’§«°Ґ°÷§™§Ў§љ§«√г§т ®§Ђ§є°„§»§в§§§¶°£
°°§Ј§Ђ§Ј§…§¶§Ј§∆°Ґ§™§Ђ§Ј§ѓ§∆§њ§ё§й§ §§§»°Ґ§Ў§љ§ђ√г§т ®§Ђ§є§ќ§Ђ°£
°°∆±µЅЄм§»§Ј§∆§Ґ§л°÷§™§Ў§љ§ђЊ–§¶°„°÷§™§Ў§љ§ђўа° §и§Є°Ћ§м§л°„°÷ “ ҐƒЋ§§°„§»§§§¶Єм§ђ•“•у•»§Ћ§ §к§љ§¶§«§Ґ§л°£§™ Ґ° § §Ђ°Ћ§т ъ§®§л§џ§…Њ–§§°Ґ§™ Ґ§ђƒЋ§ѓ§ §√§њ§»§≠°Ґ§™§Ў§љ§ќ§Ґ§њ§к§ђЉ—§®ќ©§ƒ§и§¶§Ћ ®∆≠§є§л§Ђ§й°Ґ§љ§≥§Ўјщ√г° §ї§у§Ѕ§г°Ћ§т ®§Ђ§єµёњ№(§≠§е§¶§є)§«§в√÷§ѓ§»°Ґ§™√г§ђ ®§ѓ§»§§§¶∆ж≤т§≠§»єЌ§®§∆§и§µ§љ§¶§«§Ґ§л°£
°°
°°ї≥≈мµю≈Ѕ° §µ§у§»§¶§≠§з§¶§«§у°Ћ§ќ ≤Ђ…љїж° §≠§”§з§¶§Ј°Ћ§Ћ°Ґ°÷§™§Ў§љ§«√г§т ®§Ђ§є°„§т§в§Є§√§њљсћЊ§ќ°ЎЊ–Єм±чзЅ√г° §™§Ђ§Ј§–§ §Ј§™§Ў§љ§ќ§Ѕ§г°Ћ°ў° ∞¬± £є«ѓ°“£±£Ј£Є£∞°”і©°Ћ§»§§§¶Їо… §ђ§Ґ§л°£∆ь§і§н∞¬§ѓї»§п§м§∆§§§л§Ў§љ§Ђ§й≤Љ§ќ…®° §“§ґ°Ћ§д¬≠§ќ≥∆…ф§ђ°Ґ§»§Ђ§ѓ¬зїц§Ћ§µ§м§л§Ў§љ§Ђ§йЊе§ќ≥∆…ф§Ћ§њ§§§Ј§∆»њЌр§тµѓ§≥§є§ђ°Ґ°÷зЅ° §Ў§љ°Ћ§ќ≤І° §™§≠§ °Ћ°„§ќјв∆ј§Ћ§и§√§∆§™§µ§ё§л§»§§§¶§ќ§ђ§љ§ќ•є•»°Љ•к°Љ§«§Ґ§л°£
°°њё»«§ѕ§≥§ќ ™Єм§ќЇ«љй§ќЅё≥®§Ђ§й°£§µ§лњЌ§ќ Ґ§ќ§ё§у√ж§Ћ°÷зЅ§ќ≤І°„§»§§§¶∞¬≥Џ±£µп§ђљї§у§«§§§∆°Ґ√г≥ш§«√г§т ®§Ђ§Јћћ«т§™§Ђ§Ј§ѓ л§й§Ј§∆§§§њ°£§µ§лњЌ§ђ§»§н§»§н§»§ё§…§н§у§ј§є§≠§ЋзЅ§ќ§Ґ§њ§к§Ђ§й°÷зЅ§ќ≤І°„§ђ§Ґ§й§п§мљ–§∆°Ґ…®§д¬≠§ќ≥∆…ф§ЋґµЈ±§Ј§∆Ќ°° §µ§»°Ћ§є§»§§§¶∆вЌ∆§«°Ґ§≥§ќ≥®§ќ§»§≥§н§Ћ§ѕ°Ґ°÷њЌ§т√г§Ћ§Ј§њ§»§§§’їц§ѕЇ°° §≥§ќ°Ћ≤І§и§кїѕ§ё§к§±§л°„§»љс§Ђ§м§∆§§§л°£
°°§≥§ќЄе§Ћ°÷§Ў§љ§вјЊєс° §µ§§§≥§ѓ°Ћ°„§»§§§¶ЄјЌ’§в≈–Њм§є§л°£§≥§м§ѕ°÷§Ў§љ§ђ√г§т ®§Ђ§є°„§»§™§ §Є∞’ћ£§«§Ґ§к°Ґ§Ґ§ё§к§Ћ§™§Ђ§Ј§ѓ§∆§Ў§љ§ђјЊєс° іЎјЊ∞ јЊ§ќєс°Ћ§Ћє‘§√§∆§Ј§ё§¶§≥§»°£≈цїю§ќєсЄмЉ≠≈µ°Ў–ЁЄјљЄЌч° §к§≤§у§Ј§е§¶§й§у°Ћ°ў§Ћ§ѕ°Ґ°÷њ”° §ѕ§ §ѕ§ј°Ћ§Ј§ѓ”ё° §Ґ§ґ§±°Ћ§кЊ–§’§т±Њ°„§»§Ґ§л°£∆±ЌЌ§ќЄјЌ’§Ћ°÷§Ў§љ§ђ∆ю≈в° §Ћ§√§»§¶°Ћ≈ѕ≈Ј° §»§∆§у°Ћ§є§л°„° §Ґ§ё§к§™§Ђ§Ј§ѓ§∆°Ґ§Ў§љ§ђ≈в° √жєс°Ћ§Ђ§й≈ЈЉ≥° •§•у•…°Ћ§ё§«§в≈ѕ§√§∆§ж§ѓ°Ћ°Ґ°÷§Ў§љ§ђљ…¬Ў§®§є§л°„§в§Ґ§л°£
°°§≥§ќ≤Ђ…љїж§ђљс§Ђ§м§њ∞¬± §ќЇҐ§Ћ§ѕ°Ґ°÷§Ў§љ§ђ√г§т ®§Ђ§є°„§д°÷њЌ§т√г§Ћ§є§л°„°÷§Ў§љ§вјЊєс°„§ §…§ќЄјЌ’§ђ§є§«§Ћє≠§ё§√§∆§§§∆°ҐєЊЄЌ§√ї“§њ§Ѕ§Ћє•§ё§м§∆ї»§п§м§∆§§§њ§≥§»§ђ§п§Ђ§л°£µю≈Ѕ§ѕ§љ§¶§§§√§њќЃє‘Єм§т§є§Ђ§µ§ЇЉи§к∆ю§м§∆°Ґ≤Ђ…љїж§тљс§§§њ§ќ§«§Ґ§л°£
°°
°°§»§≥§н§«°Ґ•§•у•њ°Љ•Ќ•√•»Њр у§Ћ°÷§™§Ў§љ§ђ√г§т ®§Ђ§є°„§»∆±µЅЄм§»§§§¶§≥§»§«°÷мы° §Ђ§Ђ§»°Ћ§ђ√г§т ®§Ђ§є°„§»§§§¶ЄјЌ’§ђ§Ґ§л§»°Ґ ™√ќ§к…ч§Ћљс§≠єю§ё§м§∆§§§л§в§ќ§ђ§Ґ§√§њ°£ƒі§ў§∆§я§њ§й°Ґ§≥§м§ѕ°Ў–ЁЄјљЄЌч°ў§т ‘їЉ° §Ў§у§µ§у°Ћ§Ј§њ¬ј≈ƒЅіЇЎ ‘§ќ°ЎЄЅ±с° §≤§у§®§у°Ћ°ў§Ћµт° §и°Ћ§л§≥§»§й§Ј§ѓ°Ґ°ЎЄЅ±с°ў§Ћ§ѕ°Ґ°÷мы° •Ђ°≥•»°Ћ•Ђ√г•т•п•Ђ•є°°ЄжзЅ•ЂЊ–•’°°° “ Ґ•§•њ•≠”»°“§њ§»§®°”°Ћ°„§»§Ґ§√§њ°£
°°мы§ѕ ћ§Ћ°÷§≠§”§є°„§»§вЄ∆§÷°£јщ√г§т ®§Ђ§єµёњ№§ѕ°Ґ•≠•”•Ј•з•¶Ґ™•≠•”•Ј•зҐ™•≠•”•єҐ™•≠•е•¶•є§ §…§»≤ї —≤љ§Ј§∆§™§к°Ґ°÷µёњ№° §≠§”§є°Ћ§ђ√г§т ®§Ђ§є°„§т°÷мы§ђ√г§т ®§Ђ§є°„§»ёѓЌо§м§∆Єј§√§њ§≥§»§ќ∆ж≤т§≠§«§Ґ§√§њ°£

Ґ•°ЎЊ–Єм±чзЅ√г°ў° ∞¬± £є«ѓ°“£±£Ј£Є£∞°”і©°Ћ§и§к°£њі≥Ў° §Ј§у§ђ§ѓ°Ћ§ќ√ћµЅЋ№° §ј§у§Ѓ§№§у°Ћ°ЎзЅ±£µп° §Ў§љ§§§у§≠§з°Ћ°ў° ∞¬± £≥«ѓ°“£±£Ј£Ј£і°”і©°£≤ђ≈ƒґ√Єч√ш°Ћ§т њћј§ ≥®Ћ№≤љ§Ј§њ§в§ќ§«§Ґ§л°£
ї≥≈мµю≈Ѕ...£±£Ј£ґ£±°Ѕ£±£Є£±£ґ°£єЊЄЌЄеіь§ќµЇЇоЉ‘°¶…вј§≥®ї’°£≤Ђ…љїж°¶ёѓЌоЋ№° §Ј§г§м§№§у°Ћ§ќ¬и∞мњЌЉ‘°£
≤Ђ…љїж°ƒєЊЄЌЄеіь§ќ∞¬± £і«ѓ° 1£Ј£Ј£µ°Ћ§Ђ§й Є≤љ£≥«ѓ° £±£Є£∞£ґ°ЋЇҐ§Ћ§Ђ§±§∆ќЃє‘§√§њЅрЅ–їж° §ѓ§µ§Њ§¶§Ј°Ћ§ќ§“§»§ƒ°£ёѓЌо°Ґ≥кЈќ°Ґ…чї…§т§™§к§ё§Љ§∆≥®§» Є§«ћћ«т§ѓЇо§√§њЊЃјв§ј§ђ°Ґ¬зњЌ§ќ•≥•я•√•ѓ§Ћґб§§°£
°Ў–ЁЄјљЄЌч°ў°ƒєЊЄЌ√жіь§ќєсЄмЉ≠≈µ°££≤£ґіђ°£¬ј≈ƒЅіЇЎ ‘°£і≤јѓ£є«ѓ° £±£Ј£є£Ј°Ћ∞ єя§ќјЃќ©°£¬ѓЄм°Ґ эЄј°Ґ§≥§»§п§ґ§ §…§тЉэѕњ°£
°ЎЄЅ±с°ў°ƒєЊЄЌїю¬еЋціь§ќ§≥§»§п§ґЉ≠≈µ°£¬ј≈ƒЅіЇЎ ‘°£°Ў–ЁЄјљЄЌч°ў§ѕ§≥§м§тЅэ д≤ю ‘§Ј§њєсЄмЉ≠≈µ°£
|
Ѕ∞§ќ•Џ°Љ•Є єЊЄЌ§≥§»§–Јо§і§и§я 4Јо |
•≥•у•∆•у•ƒ§ќ•»•√•„ |
Љ°§ќ•Џ°Љ•Є єЊЄЌ§≥§»§–Јо§і§и§я 6Јо |









